私が社労士受験生のとき、総務人事部で労基署の調査に対応したことについてお伝えします。
内容は「割増賃金の算定基礎となる賃金」のことについてです。
参考にしていただけることがあれば幸いです。
指導票に対する改善措置
先般(平成18年頃)のA事業場への指導票の内容に係る改善措置を進めるなかで浮かび上がった課題がありました。
それは、労基署の調査以前に新たに設けた「業績手当」の扱いについてです。
給料計算に詳しい方なら問題になるようなことではないと思われることでしょう。
しかし、私にとっては社労士受験のテキストでは習っていても実務で直接関わっているわけではありませんでした。
どういう内容かというと、割増賃金を算出するにあたり、この「業績手当」を算定基礎となる賃金に含めるか否かということです。
指導票に対しての改善措置を進めるなかで、「業績手当」を割増賃金の算定基礎に含めずに算出してしまいました。
給料計算については、私ではなく総務課の担当者が行っていました。今回も通常の給料計算の流れで算出し、その計算結果に基づいて資料を作成しました。
そして、改善措置報告に際しその資料を監督署へ提出したところ、「業績手当」は算定基礎に含めるべき手当であるとの指摘を受けてしまいました。
したがって、次月以降は当該手当を算定基礎に含めて算出した資料を作成し、報告するようにとのことでした。
今ならごもっとも と思うようなことですが、当時はそのような間違いをしてしまっていたわけです。
割増賃金の算出式
【割増賃金の算出式】
算定基礎賃金÷所定労働時間×割増率×対象となる労働時間数
分解すると
①時給単価算出:算定基礎賃金÷所定労働時間=時給単価
②割増賃金の時給単価算出:時給単価×割増率=割増賃金の時給単価
③割増賃金の算出:割増賃金の時給単価×対象となる労働時間数
となります。
算定基礎となる賃金とは
監督官からの説明は、以下のようなことでした。
算定基礎となる賃金とは、労基法第37条、および労働基準法施行規則第21条に規定されていない賃金は、全て算定基礎となる。
下記(1)~(7)以外の毎月固定的な支給であれば、名称を問わず割増賃金の算定基礎に算入となる。
(1)家族手当
(2)通勤手当
(3)別居手当
(4)子女教育手当
(5)臨時に支払われた賃金
(6)1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
(7)住宅手当※
※住宅手当を割増賃金計算の算定基礎から除外するのであれば、住宅に要する費用に応じて算定(費用に定率を乗じた額とすることや、費用を段階的に区分し費用が増えるにしたがって額を多くすること)されるものでなければならない。一律に支払われる住宅手当や、賃貸住宅1万円、持ち家住宅5千円という定額支給であれば、算定基礎から除外することはできない。
以上が監督官から受けた説明でした。
したがって、今回指摘された手当は、毎月固定額で、一部の対象者を除いてほぼ全員に支払われており、上記(5)の臨時に支払われた賃金には該当しないものとなり、算定基礎に含めなければなりません。
割増賃金算定に係る除外賃金の覚え方
参考までに、割増賃金算定に係る除外賃金の覚え方はこれです。
か・つ・べ・し・じゅ・り・い(勝つべしジュリイ)
家族手当→家族→か
通勤手当→通勤→つ
別居手当→別居→べ
子女教育手当→子女→し
住宅手当→住宅→じゅ
臨時に支払われた賃金→臨時→り
1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金→1箇月→い
か・つ・べ・し・じゅ・り・い(勝つべしジュリイ)
算定基礎となる所定労働時間とは
[労働基準法施行規則第19条より一部抜粋]
(A)日によって定められた賃金の場合→ 1日の所定労働時間数
(日によって所定労働時間数が異なる場合には、1週間における1日平均所定労働時間数)
(B)週によって定められた賃金の場合→ 週における所定労働時間数
(週によって所定労働時間数が異なる場合には、4週間における1週平均所定労働時間数)
(C)月によって定められた賃金の場合→ 月における所定労働時間数
(月によって所定労働時間数が異なる場合には、1年間における1月平均所定労働時間数)
おわりに
今回の件は、実務において直接お金(賃金)に関わることであり、給与計算業務の責任の重さを感じた次第でありました。
以上、最後までお読みいただきありがとうございました。
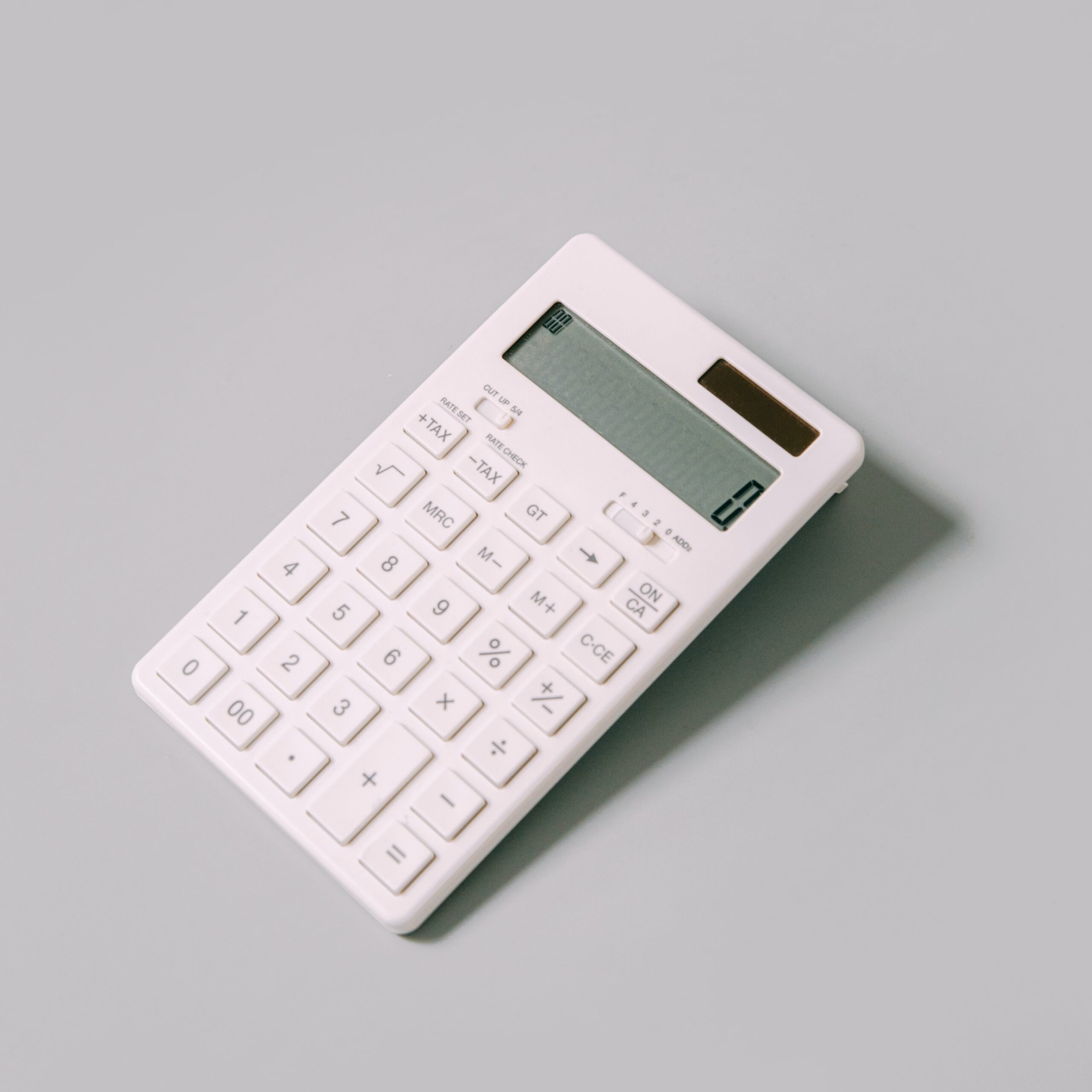

コメント